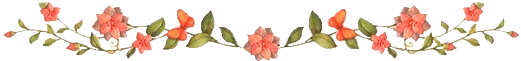
しょうちゃんの繰り言
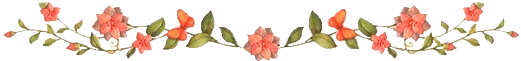
しょうちゃんの繰り言
| 会社は誰の物 |
|
古い付き合いのある、さる船会社のOBで未だに「うちの会社は」と表現する人がいる。部長職で会社を辞めて農業に従事し、少なくとも会社と縁が切れて30年位経つと思われるが、80歳近くになった彼にとって会社は永遠の身内なのだ。こういったメンタリティーは日本人には珍しくないもので、終身雇用が当たり前の時代の人に共通する感覚なのだろう。 私達が就職した頃(1960年代中期)、学生にとって一部上場企業が狙い目だったが、世間でそこそこに名の売れた会社に入社すればその後少なくとも生活は安定し、住宅ローンも何とか借りられた。厚生年金や場合によっては会社年金も期待出来、定年まで勤めれば退職金まで出る。人生設計としてはリスクが少なく、当時日本人が真面目に働いた背景が良く理解出来る。従って当時を経験した普通の日本人サラリーマンにとって自分が勤めた企業はいつまでも「うちの会社」として存在することになる。東京オリンピックや新幹線開通を自分の目で実感しながら働いた人達の共有出来る普通の感覚だろう。 前にも触れたように、その当時造船は世界一の建造量を誇り、鉄鋼生産も毎年伸びていた。あらゆる産業が国内・国外に充分なマーケットを持ち、確実に成長していた。給料の格差も少なく「社長の給料は新入社員の20倍を越さない」という神話が出来始めた頃だ。 「年齢に応じた生活給」というコンセプトが疑問無く国民に受け入れられた時代で、少々の功績を挙げても先輩の年収を追い越すことは出来なかった。それでも社会は安定し、今のような生活不安の声は大きくなかったと覚えている。年功序列給は或いは日本大躍進の基本をなしていたのかもしれないと最近思うようになった。 1970年代になると給料は毎年上昇し、同時に地価を含めた諸物価も上昇した。貨幣価値は実感として5年で半分程度になっていた。安い人件費をベースに輸出で稼ぐ図式は次第に崩れ、戦後1ドル360円だった固定相場の円も1971年には308円に切り上がった。 1973年の第4次中東戦争を契機に第1次オイルショックが始まると国内では物価の高騰が見られ、1974年には福田赳夫氏命名の「狂乱物価」という言葉が流行った時代だ。それでも、給料が上がり国内の景気が良くなれば当然人件費の高騰が生じる。 さらに為替の変動に焦点を当てて調べてみると、1973年には変動相場となり急激な円高を経験することになった(1ドル308円の固定相場から、変動相場発表後のスタートでは1ドル277円から始まった)。こういった短期間での円の急激な切り上げと変動相場制への移行は、ドルの通貨基軸国であるアメリカの経済を助けるための先進国による経済協力政策であった。 しかし、アメリカの双子の赤字(財政赤字と貿易収支)の増加はさらに1985年のプラザ合意に繋がり、その時235円だった円は合意後一晩で20円も上がった(1ドル215円)。そしてその1年後には150円台まで上がっている。その後我々は70円台も経験し、第二次安倍政権でやっと歯止めが掛り現在120円台で「円安」として推移している。それでも日本企業は大変な思いで円高に対応し、優秀な電気製品や車の輸出等で稼いでいる。だが一方で会社経営の背景は為替問題(極端な円高)によって一変した。 経済の専門家でない私にも、この急激な為替の変動を見れば日本の企業が置かれた立場は良く理解出来る。よく、ここまで頑張って来たというのが実感だ。天然資源の無い国は人間だけが資源で、原料を輸入してそれを加工し、国内外で付加価値の付いた製品として売るしかない。経済の動きや為替の変動は日本の事情だけで決まるものではなく、特にアメリカの状況が我が国の経済に影響を与えることが多かった。 人件費の高騰や円高に対し会社の採った経営方針は出来るだけ人を減らすことだった。各部門で「リストラ」という名の下で人減らしが始まり、生産ロボットの活用、コンピュータの活用と全ての企業は組織のスリム化を図り、特に船会社は人件費の高い日本人船員を回避して安い外国人船員にシフトしていった。これも企業が生き残る為の窮余の策だったと言える。 その後、自動車を含めた各種生産工場も人件費の安い海外へと移され、国内の労働力は会社から見て調整しやすい臨時工や、派遣社員の活用へと大幅に転換された。これも会社の固定費(割高になった人件費)を削減するための生き残り策だった。自由競争を基本とする資本主義の世界では、それぞれの国がそれぞれの国内問題を抱えて現実的な対応策を取り、日本だけが例外だったわけではない。国際的競争に晒された場合、企業は究極の生き残り作戦を取らざるを得ないだろう。従って、派遣社員の現状を一方的に政府や企業の経営者を非難して解決出来る問題ではない。 日本の技術と安い労働力に敗退して衰退した海外の企業は、アメリカの自動車産業だけではないだろう。電気製品や光学機械の分野でも日本の戦後の躍進は目覚ましいものがあった。現在、日本の人件費が国際レヴェルになり、むしろ1ドル100円台の円高で高止まりしている時、我々の真価は問われている。鉄道・航空機・付加価値の高い造船(客船・防衛力の充実した自衛艦)それにIT技術の革新とそれを応用した宇宙ロケット・防衛システム等々、今後日本の技術者に期待されている分野は幾らでもある。クリーンエネルギーの応用とさらなる開発・革新的な生命科学・安全な農業生産物・環境改善技術の輸出・高度医療技術及び医療機器の開発と普及、等々思い付くままに並べてもいくらでも出てくる。 私ごときに解決策は出せないが、少なくともアメリカかぶれの経済学者が唱える小手先の聖域なき改革で日本や世界が良くなるとは思えない。今我々に必要なのは、目先の金融主導による経済戦争での一時的勝利ではない。資本が自由化された時、理念無き弥縫策で対応していては単に海外の大資本を喜ばせるだけだ。韓国の財閥企業が海外資本に株を所有されているため、利益が韓国内に還流されてない現実が最近明らかにされている。日本でも大店法の解禁を喜んだのは誰かをよく考えた方がいい。その結果、地域商店街にシャッターが下ろされた例なら日本中どこでも見られる。時代の波に呑まれたと言えるかもしれないが、こうやって地域が破壊され人の絆も消えている。社会は経済の法則が全てに優先する訳ではない。 そして、どうしても言っておかなければならないのはアメリカ金融主導の「グローバル・スタンダード」など極論すれば日本では何にも役に立たないということだ。前にも触れたが、アメリカのノーベル賞を受賞した経済学者ミルトン・フリードマンは所謂「新自由経済」の提唱者として知られていて、全ての経済活動を市場に任せ、極論すれば「あらゆる経済活動は社会的使命を考慮する必要はない」とまで彼の経済理論は解釈されている。それに対してシカゴ大学で同僚だった宇沢弘文教授は終始批判的だった。 金融万能主義で足かせを外せば金融が暴走することくらい無学の私にでも判断出来る。リーマン危機はフリードマンの「経済的自由放任主義の産物」とまで決め付けた経済学者が日本の宇沢弘文教授だった。 何度か例に出したが、日本ではパイプを咥えた評論家と「ミスター円」と呼ばれて得意満面の大蔵省OBがテレビで盛んに金融商品の開発を煽っていた。両者の言い分は「アメリカでは30%以上の利回りを出す金融商品を開発している、一方、日本の銀行金利は1%にも満たない」という理論展開だった。例の口の悪い友人はすぐにこの説の幼稚さを見抜いて「こいつらの言い分を聞くと、碌なことにならない」と吐き捨てていた。 リーマン・ブラザースがサブプライム・ローンの金融商品で破綻する前の彼等の御高説だったが、2008年に破綻した後は何の総括も両者からなされてない。 投資する側からは、1%未満の金利と30%以上の利回りとでは、どちらが儲かるくらい二人に教えて貰わなくても分かるが、問題はこの金利での経済的継続の妥当性だ。この金利なら3年間で投資金額が倍になるが、ごく普通に考えてこんな虫の良い話が何年も続く筈がない。 念の入ったことに、この「ミスター円」はリーマン・ブラザース破たん直後、「ドルは60円台になる可能性があり、又ドルは世界の通貨基軸から外れる可能性もある」とさらなるご高説を懲りずにテレビで披露していた。明言してはいなかったが、中国の元をドルに代わる将来の基軸通貨と想定しての発言だったことは明らかだ。 50年・100年単位の話なら分からないでもないが、リーマン・ブラザースが破綻したのを契機に発言していることから彼の予言は数年単位での見通しと判断するのが妥当だろう。あれから7年は経っているが、ドルは依然として世界の通貨基軸で、現在1ドルは120円台だ。なお、中国の元に関しては国際的には「安定した通貨」という信頼はまだ得られていない。国自体が信頼されず、安定もしていないのに通貨が世界基軸になる訳はない。 前にも触れたように、大蔵省のキャリアー達は現東京都知事によれば日本で一番優秀な人の集団となるが。例の友人の表現を真似すれば「ミスター円」の発言を聞くにつけ「どこが(優秀)」となる。普通こういう無節操な発言を恥の上塗りと呼んでいるが、本人は一向に懲りず、ヘラヘラ笑いで未だにテレビに顔を出している。 残念ながらこの程度のテレビ評論家でも日本では立派に飯を喰えるし、教授として喜んで迎えてくれる大学は幾つもある。友人なら、この場合「学生が可哀そう」と言うだろう。 金融が支配するアメリカの資本主義社会では「会社は株主のもの」という説が主流になり、日本でも追随する経済学者が増えているようだ。確かに経済学的理論構成では「会社は株主のもの」と定義しても間違いはないのだろう。しかし辞めて30年近く経っても「うちの会社」と発言するのが日本人のメンタリティーの基本をなしていることを考えれば、底の浅い経済理論に日本が従う必要はない。金融といえども社会的使命は大いにあるし、影響力が大きいだけに余計に彼等は配慮しなければならない。日本は、「政治は三流だが経済は一流」と言われた時もある。理念を忘れた時、その格付けはすぐに下がるだろう。 終生「うちの会社」と誇りを持って言えることはそこに働いた人間にとっては嬉しいことだろう。金融で小銭を稼ぎペットの犬に「大間のマグロ」を食べさせていたバカ・カップルまでいたが、可哀そうに彼等は損をした顧客の犠牲になった。ペットの犬を除けば事件当事者の彼等は全て経済という喜劇での犠牲者だ。半端な奴が儲かり、半端な奴が損して引き起こした人間喜劇にしかすぎない。終生「うちの会社」という喜びも誇りも彼等にはない。 前にも出した例だが、私達世代が現役で働いていた頃の「社長給料は新入社員の20倍」理論によれば10億円社長に払う会社は5,000万円の初任給を払わなければならない。それなら誰も異論を唱えないだろうが、大卒にすぐ5,000万円払う企業はない。だとすれば社長の給料を初任給の20倍以内に自主規制(?)していたのが間違いなのだろうか。資本主義経済本場のアメリカではトップの年収が10億程度はざらに居て、ひと桁違う収入さえ見られる。 日本で10億円貰っている社長も良い人材を確保するためには高給である必要性を主張していた。あの程度の人材で良ければ日本にはいくらでもいたし、日本人なら決して10億円を受け取らなかっただろう。新入社員の20倍でも黙ってその責を引き受けていたに違いない。この精神性の高さをラテンやアングロサクソンの商売人に説いても無駄だ。彼等は貪欲に己の利益を求めるだけで、会社は株価を高くして株主に評価されるのを第一義と考えている連中だ。アメリカに粉飾決済が多かったのもそのためだが、今では厳しく監視されているそうだ。 経済の話になるとうんざりすることが多いが、日本には良いニュースもある。アジアで突出したノーベル賞受賞者の数は、日本の各分野の基礎研究が充実していた何よりの証明で、国にはさらに力を入れて欲しい。人材が唯一の資源である日本は有能な若者が良き伝統を引き継いでくれるものと思う。いつも言うことだが、一過性の利益など空しいものだ。 自分の働いたとこを終生「うちの会社」と誇りを持って言える時代がまた来て欲しい。 平成27年7月27日
■
|