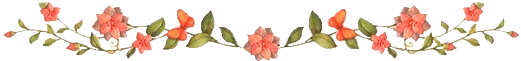
しょうちゃんの繰り言
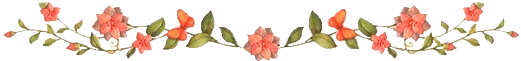
しょうちゃんの繰り言
|
後期高齢者の企み |
| 壺井栄の「二十四の瞳」を読んだ時、“10年をひと昔というならば、この物語の発端は今からふた昔半もまえのことになる”という書きだしで始まる文章に、これは随分昔の話なのだなと思ったことを憶えている。10代の少年に10年・20年という年月はとてつもなく長く感じられたものだった。 小学校の6年間、中学の3年間はとても老境に達して感じる時間の単位では計れぬ長さだった。学んだり思い出を作ったりする時期は時がゆっくり進むのだろう。それは高校時代も大学時代もあまり変らなかったような気がする。時はゆったりと流れ、知恵もゆっくりと育まれる。 ■ どうも時間経過の感覚は年代によって違うようで、特に還暦あたりからの時間はあっという間に過ぎ去ってゆく。子供の頃“少年老い易く、学成り難し”と教師に言われても何の実感も伴わなかったが、この年になると良く分かる。年配者の警告が頭の上を通り過ぎるのはいつの時代でも同じで、“親のありがたさは子供を持って分かる”といった類の教えも子供を持つまで実感出来ないものだろう。年をとるという事はそういうことで、自分の経験から若者に同じ説教をしたくなるが、それを聞かされている若者も真意を理解する為にはそれから何10年もの時が必要なのだろう。秋の夕陽のつるべ落としではないが、晩年の残り時間が早く過ぎるようになって突然色々と見えてくるものがある。時は長いほど、過ぎてしまえばあっという間だ。 ■ 高校同期の古希の祝いに出たとき、仲間の物故者は約1割だった。これは多分統計上標準的な数字なのだろう。10年後にお祝いを又やろうという話になったが、何人残っているのか、残っていてもその内何人が現場に出かけられるのか心もとない話だ。古希からの10年はつるべ落としの速度は確実に加速され、自分が残る自信は全くない。こればかりは自分の意志や努力では果せないものがありそうだ。天命には逆らえないという諦観が当たり前になる年代なのだろう。平たく言えば死が身近になり、他人事ではなくなる年齢だ。孫をいとおしく思うのも、残り少ない生体の生きることへの執着心から来ているのではないだろうか。求めるものもその必要性の判断に自分の残りの時間が常に頭にあるような気がする。新しいことに挑戦する気が衰えるのも残りの時間を無意識に自覚しているからだろう。 ■ そんな年代の後期高齢者が頭を悩ます現実的問題は冠婚葬祭時の出費だ。少数の例外を除き年金暮らしの身には切実だと感じる人もかなりいると思われる。周りの友人は自分と同じ様に年を取り、特に学校の同期で仲良く纏まっていた分それぞれが徐々にお隠れになる際、残った仲間は年金からその都度香典の出費となる。最後に残った人は全部に付き合うわけだが、その人は居なくなった同級生からの香典は期待出来ない。損得の問題ではないが、現実こういう現象は間違いなく起きる。 大学の後輩が面白い試みを教えてくれた。彼らは仲間と話し合い、生前香典を集め、それを最後まで残った者が独り占めするというアイディアだった。つまり香典はこのルールを決めた時、全員が一回払えば終わりで、プールされた金は最後に残った人への同期からの長寿祝いとなるらしい。 死ぬことが目の前の現実と取れる年代に差し掛かり、洒落たアイディアを考えた後輩のグループに思わず笑ったが、同時に年金生活者の懐具合を考慮した思いやりのある決め事だと感心もした。彼らの真意は別として、生真面目過ぎる我々日本人も死に対してこの位の気持ちのゆとりを持ったらどうだろう。古希を過ぎれば死は単に悲しむことではなく、よく生きたと皆でお祝いしてあげることも考えようでは出来るだろう。 ■ 今の流行(はやり)では、死んでからの実務的かつ経済的処理ばかりに焦点が当てられ、遺族間で揉めないよう生前に準備することを薦めている。考えてみれば空しいことおびただしい。 ■ いつもの口の悪い友人は“人間誰しも人生で3回は主役になれる。生まれた時と結婚した時、それに死んだ時だ”と笑い、“死んだら誰でも善人になるし、立派な人になるぞ”とさらに付け加えた。からかい口調で本質突くのが彼の特徴で、言われてみればその通りの気もする。葬式が世間の慣わし事だとしても、あまりにも形式的過ぎるのは何か心が通ってないと思うのは私だけだろうか。冠婚・葬祭が一分違わず業者の仕切りで能率的に執り行われた時、何か違和感を覚えてしまう。 ■ 一見ふざけたお遊びに見える香典独り占めの後輩の約束事も、彼らなりに友人との別れに親しみを込めた演出をしたと思えば立派に血の通った儀式だと言えよう。仲間内だけに通じるユーモアに満ちた企みが、逆に彼らの結束の固さを示している。 ■ かの白州次郎氏は最晩年に大学時代からの親友だったロビン氏とイギリスの田舎で再会したが、その別れに際し明日でも又会うような挨拶を済ませ、車に乗り込むとすぐ出発するよう命じた。運転していた娘婿は気を利かせてロビン氏を見送るよう薦めたが彼は拒絶し、ロビン氏も白州氏も互いに振り返ることもなく別れていった。二人ともそれが最後の別れとなることは当然分かっていた。究極の男のダンディズムを感じさせる場面だ。貴族と武士の最高の儀式を見た思いがする。 ■ さらに白洲夫人の証言によれば彼は親しい友人の葬儀にも出ないことがあったらしい。彼と友人との別れは一人だけでやりたかったのだろう。世の習い事と、画一化されたものから超越した男の生き方が偲ばれる。 ■ 口の悪い友人は偶然だが、白州氏と似た様な遺言を準備している。「葬式不要・坊主呼ぶな・戒名要らない・香典貰っとけ」という彼らしいものだが、奥さんは“葬式しないでどうやって香典貰うのよ”と笑っている。 その彼が“古希を過ぎたら「冠婚葬祭ご遠慮」というのはどうかね”と提案してきた。高齢者社会の先駆け組としてはこういった問題提起は真剣に考えるべきかもしれない。ついでに年賀の挨拶も彼は来年から「ご遠慮」と話していた。 ■ 残った伝統や習慣にはそれなりの意味がある。だが、それが形式化し負担になった歳でも人はなかなか自分から止める勇気がない。かつて安倍総理の祖父岸信介氏は長生きの秘訣として「義理欠く・恥かく・風邪引かぬ」と言っていたと覚えている。晩年の生き方として示唆に富む言葉で我々凡人も見習ってもいいだろう。 ■ 団塊の世代を後に控えている我々が、後輩達の選択肢として古希を過ぎての「冠婚・葬祭・年賀のご遠慮」を口の悪い友人の考え通り提案するのも案外いいことかもしれない、と思うようになった。 ■ 人生を畳むのと別れの儀式には何か新しいことを企みたいものだ。ボケかかった、ちょい悪老人の最後のあがきとしては面白いと思うのだが。 平成25年2月14日 草野章二 |