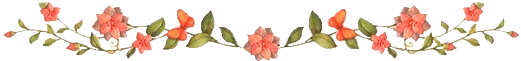
しょうちゃんの繰り言
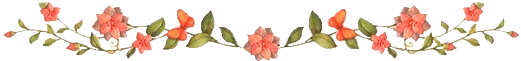
しょうちゃんの繰り言
|
曲(うた)への思い入れ |
| 音楽には人それぞれの好みがあり、好きなジャンルがある。そんなに好きでなくてもジャンルを超えて圧倒的な歌唱力で君臨した歌手も居た。戦後の日本を明るくしてくれた曲として有名な「リンゴの歌」は国民皆が貧しい中で誰もが一度は口にした代表的なものだろう。美空ひばりが天才歌手として世に出てきたのは小学校の頃だった。彼女はラジオや映画で取り上げられたちまち国民的な歌手としてその名を馳せた。彼女の一線での活躍は死ぬ直前まで続いた。音楽への特別な興味が湧いたのはNHKから流れていた「雪の降る町を」(1953年)という歌を聞いた辺りが最初ではなかっただろうか。その前に同じNHKで放送されていた「鐘のなる丘」(1947〜1950年)の主題歌「とんがり帽子」も未だに耳に残っている。外で遊んでいてもその放送が始まる夕方5時過ぎに、主題歌が何処からか聞こえてくると子供たちは家に帰った。小学校の頃、隣家から聞こえてきた曲はいつも川田正子の歌う「森の子山羊」だった。隣家には当時高価だった電蓄があって、主に童謡が流れていた。童謡・流行歌を含め、子供の頃聴いた曲は沢山あった。しかし子供心にも「雪の降る町を」の曲はインパクトがあった。哀愁を帯びた歌詞とメロディーは、内容を良く理解したかどうかは別として、それまでにない何かを13歳の子供に与えてくれた。 ■ 映画「禁じられた遊び」(日本公開1953年)の主題歌「愛のロマンス」を中学生の頃聞いた時の衝撃はさらに強かった。確かラジオのドキュメンタリー番組で、九州の洞窟に住みついていると説明のあった青年が弾いたギターの曲「愛のロマンス」を初めて聞いたが、何とも言えない精神の昂ぶりを感じた。勿論当時映画も見てなかったし、この曲に対する何の先入観もなかった。それでも初めて聴いたその旋律に心奪われたと言っても過言ではなかった。 ■ 映画の主題歌もその時代を思い出させてくれる。子供の特権として、流行歌は何度か聴くと歌詞を覚えてしまい、未だに歌うことが出来る。年齢からして過去を懐かしむ年台に入っているのは自覚しているが、これほど過去の出来事と直結している脇役はいない。小学時代から中学・高校時代に至るまで必ず当時流行った曲や歌が自然に他の出来事と結び付いて思い出される。テレビの無かった時代はラジオや映画が我々に歌曲を提供し、その中から好きな、或いは魅了された曲を心に刻んでいたのだろう。 ■ 音楽に魅せられるという現象はどうも人類共通のようで、その証拠に人種・国籍・宗教を超えて世界的人気を博する曲や歌手が出て来る。何が人をしてそうさせるのかは心理学者に任せるとしても、個人的に心引かれた歌曲は幾つもある。その曲の数々は不思議と思い出と結び付いている。日本には“歌は世に連れ、世は歌に連れ”という言葉があるが、過去の節目になる思いでには当時流行った歌が自然と浮かんで来る。逆にその歌が流行った時代が色々な思い出と共に蘇る。これほど互いに強く結び付いていることを今まであまり認識していなかった。 ■ 世代を越えて皆が歌に熱狂し、カラオケが世界的に流行っているのも何となく納得出来る。私たちが単に労働とパンのみで生きているのではないことがこういったことからも判断出来る。 ■ 昔、貴族の特権だった音楽の楽しみは、時が変りやがて一般庶民の間にも広まり、世界的演奏家・歌手・オーケストラが日本でも鑑賞出来るようになった。ここまで高めたのはやはりかつての王侯貴族階級で、彼らの庇護がなければクラッシク界の名曲の数々も生まれてこなかっただろう。絵も同じ様に彼らの庇護で芸術の域まで高められた。音楽や絵の基本は王侯貴族が培ったことは間違いが無いが、その良さは貧富・国籍に関係なく誰もが楽しむことが出来る。料理にも或いは同じことが言えよう。文化の発展・浸透には古今東西財力と権力を持った時の支配階級が重要な役割を果たしていて、彼らが表舞台から退いた後も人類の文化遺産として残ってきた。音楽のみならず文学・絵画・オペラ・バレー・料理・衣服・髪型、等々に至るまでその遺産は現代に受け継がれて来た。
かつてヨーロッパでは特出したテノール歌手を神に選ばれた存在として高く評価し、それなりの対価を払った。亡くなった三大テノールの一人、ルチアーノ・パバロッティーは世界でも最高のギャラを取り、ワン・ステージ30万ドルと言われていた時期もあった。 ■ 音楽にどの程度のめり込むかは別にして、各人それぞれの好みのジャンルで好みの歌曲を楽しみ、今では誰もがカラオケで披露する歌も何曲か揃えている。 ■ 戦後教育を受けた私達の世代はなんと言っても憧れの国はアメリカだった。映画でしか知ることは出来なかったが、当時、戦後の日本と比べ圧倒的な物量の差と、生活レベルの高さは我々の手にすることは不可能に見えた。映画のスター達に対しても、その彫の深い顔立ちや背の高さに圧倒され、とても我々が身近に感じる人たちではなかった。 テレビが一般に普及するまでは映画で彼らの姿を眺め、彼らの生活を垣間見るだけだった。そこで流される音楽には無条件に魅かれ、つたない英語で真似して唄ったものである。我々が目指したのはアメリカで、彼の国はまさに憧れの国としか当時表現の仕様が無かった。 ■ 日本は戦争に負け、結果として国民は「鬼畜英米」と蔑称・非難した国の実態を知ることとなり、その国力の差に抵抗する術を失くし、逆に憧れる存在となっていった。原因はともあれ喧嘩する相手ではなかったということが判った。戦後の日本が進駐軍に対し従順で表立った抵抗が無かったのは、彼らの実態は別として一般国民には怨念や敵愾心を掻き立てるものが表面的には彼らに見られなかったからだろう。思いつめて熱病に冒された如く猪突猛進した国民は、むしろ自分達のリーダーの誤った判断と指導に疑問を持った。戦時中、言論が統制され情報の乏しかった国民が民主主義の洗礼を浴び、一気に開放されたのはある意味歴史の必然として歓迎すべき事だったのだろう。今の我々の原点はそこにある。見誤ったものや行き過ぎたものはドサクサの副産物として必ず出てくるし、それは時間を掛けて修正出来る。戦後、基本的人権の確立や言論の自由が我が国民に与えた影響は計り知れない。その開放感の延長上にアメリカ文化があり、アメリカ音楽があった。国民のエネルギーが負の方向へ向かわなかった歴史上のいい例であろう。お陰で日本は目覚しい経済発展を遂げた。 ■ 私達世代の大学時代(1960年代前期)はウェスタンやハワイアン音楽の全盛期で、各大学には複数の学生バンドが乱立していた。中には本格的なフルバンドのある大学もあった。今と比べれば学生はまだ貧しかったが、それなりに工夫して楽器を集め何とかバンドの体裁を保っていた。その中から後に世に出た人も少なくない。残念なことに今ではジャズもウェスタンやハワイアンもかつての勢いが無く、テレビでもなかなか取り上げることは無い。時代の流れと言ってしまえばそれまでかもしれないが、60代・70代がまだ元気な内は昔流行った曲を時には取り上げて貰いたいものだ。若い娘が集団で唄うのや、アイドルと称する連中が唄う金の取れない歌にはおじさん達はあまり興味がない。決して否定はしないが大人の時間も時にはあってもいいのではないだろうか。番組を制作している若い連中にバランスを取れと言っても何だか無駄な気もするが。文化の担い手をあざとい商業主義に徹した連中に渡してしまっていいのだろうか、という疑問は依然として残る。少なくとも金を取って放送しているところでは特に配慮して貰いたいものだ。昔、日本でも放送していた「エド・サリバン・シヨー」というアメリカの人気歌番組があったが、司会のエド・サリバンは必ずオーディションやり、彼のお眼鏡に叶わなければ番組に出すことはなかった。人気が出始めたビートルズもその例外ではなかった。まさしく彼の見識で番組の権威が守られていた。日本では金を貰って唄ってはいけない連中がテレビに多く出ている。大人のプロデューサーは日本には居ないのだろうか。 ■ アメリカのポップス界では時代を超えて残る曲や歌を「スタンダード」として別格の扱いをしている。一過性で流行っても残らない曲はスタンダードとして認められない。我々の時代にはスタンダードとして残ったいい曲が沢山世に出て来た。そんな曲の数々は我々の青春の思い出と共にいつまでも我々の遺産として残っている。何よりもメロディー・ラインの美しさが我々の心を捉えた。映画「慕情」(1955年公開)の主題歌「Love Is a Many Splendored Thing」は映画のディテールは忘れてもこの曲は強烈に記憶に残っている。西部劇の名作「シェーン」(1953年制作)のBGM「遥かなる山の呼び声」(The Call for Far-away)も当時の若者を魅了した曲だった。1960年代の初頭「ティファニーで朝食を」(Breakfast at Tiffany’s)の中でオードリー・ヘップバーンがギターを奏でながら歌った「ムーン・リバー」(Moon River)は今でも広く愛されている。すぐに当時の曲が幾つも出て来る。 ■
個人的好みで言えばフランク・シナトラの大人の雰囲気が一番気に入っている。彼の代表的な「マイ・ウェイ」(My Way)はその歌詞に私たち年代は身につまされるものがある。 “And now the end is near and so I face the final curtain”(今や終わりが近づき、人生最後の舞台に立っている)この歌詞はまさに古稀を過ぎた連中の実感ではないだろうか。 今や伝説(Legend)となったシナトラ、パバロティーの生の舞台を鑑賞出来ただけフアンとしてはまだ善しとすべきなのだろう。同時代に生きた者の特権かも知れない。 ■ 戦い済んで日が暮れて、“さて私の行くとこは”となると漠然とした不安が先に見えるだけだ。これが老いというものかもしれない。老人性うつ病はそんなに珍しい病気ではないという。そんな後期高齢者のテンションを上げるのが青春時代を彩った曲の数々だ。損や得を乗り越え確実に浸れるもの、他の言葉では逃げ場が誰にも用意されている。それが想い出の曲なのだ。 ■ カラオケで先の短い老人が歌う「マイ・ウェイ」をどうか寛大な気持ちで聴いて欲しい。彼には若いあなた方ほど時間が残されていないのです。 平成25年4月15日 草野章二 編集人注: われわれの年代のオジサンは敵国音楽といわれたジャズが好きな人が多い。日本では「スタンダード・ジャズ」という言葉がよく使われる。もちろん、アメリカでも”Standard Jazz”という言葉は単なる流行歌と区別する単語である。 しかし、アメリカでも音楽にうるさい人種は”The Great American Song Book”という言葉を使うようだ。1920年から1950年にブロードウェイ・ミュージカル、映画音楽などのために生み出されたアメリカのポピュラー・ソングの中で最も重要で最も影響をもたらした作品の「基準(canon)」のことをいう。 具体的には、評論家で作曲家のAlec Wilderが1972年にアメリカのポピュラー音楽作家の作品とその曲・詞について詳細に分析・批評した”American Popular Song : The Great Innovators, 1900-1950”という本を書いた。この本を「基準」として、作曲家・作詞家・楽曲を評価し、Wilderの基準に相応しい作者と楽曲を”The Great American Songbook” と呼んでいる。 巨匠Irving Berlinに対しても痛烈な批評を書き、Berlinは激怒したという話が伝わっている。そのためこの本にはBerlinの譜面は一切掲載させなかったという。そのIrving Berlinを含めて6人のコンポーザーには各1章を個別に書いている。 Jerome Kern, Irving Berlin, George Gershwin, Richard Rodgers, Cole Porter, Harold Arlen 次は2人で1章、 Vincent Youmans, Arthur Schwartz 次は3人で1章、 以下のコンポーザーは「偉大な職人」という章に入れられている。 Hoagy Carmichael, Walter Donaldson, Harry Warren, Isham Jones, Jimmy McHugh, Duke Ellington, Fred Ahlert, Richard A. Whiting, Ray Noble, John Green, Rube Bloom, Jimmy Van Heusen これらのコンポーザーの作品以外にも素晴らしい作品が残されているので、章を改め”Outstanding Individual Songs”に多くの名曲が取り上げられて分析・評論されている。(2013/7) |