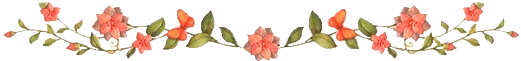
しょうちゃんの繰り言
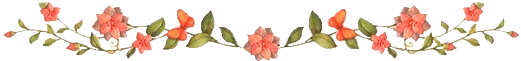
しょうちゃんの繰り言
すべて世は事もなし |
| ポール・ヴェルレーヌの詩「秋の歌(落ち葉)」(拙文「言の葉」参照)と同様、これも上田敏の訳になるが、1905年に発行された彼の「海潮音」に、イギリスの詩人ロバート・ブラウニング(Robert Browning 1812〜1889)の「春の朝(あした)」という短い詩が共に紹介されている。
原詩でも、極めて分かり易い言葉で自然を淡々と謳っている。 ところが、この詩は長編詩劇とでもいう長い物語の中に出てくる、ほんの一節にしか過ぎない。通りすがった少女ピッパ(Pippa)が唄うこの詩を聞いて、愛人の夫を共謀して殺した主人公の不倫カップルが、いたく人生を反省するきっかけになる場面の詩だ。 記憶が定かではないが、この詩は長崎時代に学校(大学時代以前)で習ったと覚えている。但し習ったのは、この短い小節の詩だけで、この詩の背景に関してはその時教わった覚えがない。 しかし考えてみれば、この物語の境遇にある人間のみならず、読む人各人がそれぞれに解釈出来る詩でもある。何かしら心に引っかかるものがある時、無垢な少女がこの詩を唄えば心に共鳴するものが生じてくるのだろう。失意の時、高揚している時、そして如何なる人生の場面に於いても、この詩はあたかも自然の風景そのままに私達に寄り添ってくる。華麗な修飾語もなく、凝った比喩や暗喩もなく、無心に少女が自然を在りのままに唄う詩に心魅かれている自分を、それぞれがやがて自分に重ね合わせて見ることになるだろう。人の営みには裏も表もあるが、そんな瑣末な人の係わりには関係なく、今日も明日も自然は泰然として「すべて世は事もなし」と時を刻んでいる。短い言葉と表現で神と自然の偉大さと、人間の存在の儚さを謳ったものだと解釈するのは私の考え過ぎだろうか。 夏目漱石、芥川龍之介もブラウニングの詩を高く評価していたエピソードが残っている。だが、この事実を知ったのは最初にこの詩に出会ってから大分時が経っていた。 この平凡な言葉で語られる自然の風景が、時代を超えて何故これ程評価されるのか分かるような気がする。人生50年と言われた時代とは我々は今や別次元のような世界に生きているが、古稀を過ぎた残り時間の少ない人間には“すべて世は事もなし”という結びの一節がそれぞれの感慨で胸に響くことになる。誇れる日々も、思い出したくない日々も、長く生きていれば生じるに違いないが、いろいろな場面でこの詩は別の言葉を私達に語りかける。若き日に聞いたこの詩の“すべて世は事もなし”が意味するものは、同じ言葉でも昔聞いた時と今日の感慨とは当然違ったものだ。ただ事実は、表現された言葉としてはこの詩は最初出会った時から一字一句、何ら変わっていない。 これに類した詩や文芸作品の一節は、誰にも自分の珠玉のものとしていつまでも残っていることがあるだろう。そして、そういった我々の心に時を超えて残るものこそが名作と言われる所以なのかもしれない。 幼き日の拘り、青春時代の拘り、そして社会に出て仕事を始めてからの拘りと時系列に比べてみても、それぞれに明確な違いがある。特にビジネスで損得勘定を常に意識して生きる頃から自分が大事にするものが段々と変質していった様がはっきりと分かる。人生の幕を降ろす時、他からの評価はともかく、自分が自分に下す評価は紛れもない本人の歴史であり、偽りの無い自分が歩んだ道そのものだ。そこに何の衒いもなく胸を張れる人は幸せとしか言いようがないが、多くの場合忸怩たる思いが常に付き纏うことだろう。 多くの思い出したくない過去を含めて、もし悔悟と贖罪意識で許され、己の小さい邪な出来事など「すべて世は事もなし」で済ませて貰えば本当に有難い。又逆に少々の栄達など「すべて世は事もなし」で葬られることにもなる。「神、そらにしろしめし」て、神の言葉として「すべて世はこともなし」と我々人間に許しを与えて下さるのであれば、異教徒と雖も有難くこの御託宣を受け止めたい。 一方、現実世界では経済で全てが計られる世の中に、最近海外を含め方々で疑問の声が挙がっている。昨年亡くなられた世界に誇る日本の経済学者宇沢弘文博士は、1976年ノーベル経済学賞を受賞したアメリカのミルトン・フリードマン(Milton Friedman 1912〜2006年)が提唱する新自由主義経済を否定し、シカゴ大学で同僚であったこのノーベル賞学者に終始批判的であった。どちらにノーベル賞を与えるべきだったかは、今ではもう結論が出ていると言っても間違いないだろう。経済には門外漢の私でもその位の判断力ならまだある。 新自由主義の経済活動は、極論すれば企業の社会的使命など考慮する必要はなく、経済効率、つまり儲ける事を追求するだけで充分だと分かり易く解説してあった。その分かり易い理論で邁進した資本主義先進国アメリカでも既に反省の動きが見えている。真似した日本にもアメリカ同様、所得格差で生じた貧民層が社会問題となっている。リーマン・ショックも正に「新自由主義経済」のお陰で出てきた現象だ。挙句の果てに後始末を全世界でやらされた。こんな現象を生みだした経済理論には宇沢博士は同調出来なかった。若くしてシカゴ大学の教授として迎えられた宇沢博士には、察するに経済を単に金融の仕組みだけから説く経済理論には賛同出来なかったのだろう。 経済の勉強もせず、その仕組みを熟知してない私が正当な評価や批判が出来るとは思ってないが、人が生きると言うことは金勘定とその尺度の評価だけで済まされるとも断じて思わない。人の生き甲斐に通じない経済活動は単に金儲けに走る輩を助長するだけで、むしろ少数の成功者の突出した分け前は社会の不安定にも繋がる。富を少数の人間で独占した時、必ず社会は崩壊している。金融の仕組みで活性化するのは金の動きだけで、これで経済が活性化しても万人の幸せには必ずしも繋がらない。どこの国でも、少数の金持ちの出現は当の本人以外誰も望んではいない。 自然や、子供の目には少々の資産や栄達など何の価値も無いものだろう。弱肉強食の世界が如何に人心を蝕むか、そしてその宴がしばらく続いたとしても、終わった時残るのは「すべて世は事もなし」の人間の営みを超越した自然の世界だけだろう。人が集まれば必ず上手く立ち回る人は出てくる。それが全体として歓迎されるものであれば大いに活躍して貰いたい。人が生きている内のつかの間の栄華は決して永続性のあるものではない事を歴史は証明している。許されたルールの中で手にした報酬が幾らになろうと、その富は同僚の共同作業と金を払ってくれる顧客があって初めて手にすることが出来る。資本主義先進国のトップの報酬は既に社会通念上のバランス感覚を遥かに越した額になっているのは誰もが分かっている。どんな事業でも、どんな優秀なビジネスマンでも個人だけの力で巨額の報酬を手にすることは不可能だ。 毎度繰り返しているが、飽くなき利益の追求を認めた時、必要以上に手段を選ばず富だけを求める人間が必ず出てくる。これは人間の持つ業みたいなもので、ここに良識ある判断力を求めても上手くいかない事が多い。それでも人間の英知を信じて少しでも多数の幸福の為何らかの手段を取らなければならない。それを変えられるのは教育しかない。 我々はブラウニングのこの短い詩に共鳴する感性を持ち合わせている。他人を思いやる心も持っている。少しばかり相手の立場を考える余裕があれば、社会はもっと別な意味の活性化が可能だろう。我が資産、我が領土と果てしなく欲望を膨らませる為、個人でも国家間でも争いの種が尽きない。 アングロサクソンの出だと思われるロバート・ブラウニングが日本人の感性に近い詩を19世紀に詠んだのが興味深い。宗教と歴史や伝統が違っても人の求めるものには普遍の共通点がありそうだ。 一過性の過剰な利益を求める姿は何人であれ美しいものではない。この短い詩を穏やかな気持ちで鑑賞出来るようになった時、もしかしたら世界は変わるかもしれない。短い命をもっと価値ある事に捧げるべきだろう。 「すべて世は事もなし」という天からの言葉を、平静な気持で現世でも黄泉の国でも聞く事が出来れば、国も宗教も越えて平和裏に共存出来る世界が実現するかもしれない。その為には我々の経済第一の価値観を少し変える必要がありそうだ。 平成27年1月6日 草野章二
|